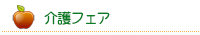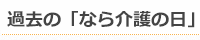≪親守唄大賞受賞≫父のぶかぶか黒い靴(作詩・作曲の部)
≪優秀賞受賞≫「母への手紙 〜秋の夕暮れに(作詞の部)
ほおずき(作詩・作曲の部)
春の日に・・・(作詩・作曲の部)
見つからない言葉(作詩の部)
野崎和俊・能智星悟「父のぶかぶか黒い靴」(作詩・作曲の部)
さくら小学一 入学日
玄関仲良く 並んでいる
僕のま白 運動靴
父のピカピカ 革の靴
誰もいないし 見ていない
大きい靴を 履いてみた
するりと足が 入ったよ
足を上げれば 重すぎて
一歩踏み出し 直ぐ抜けて
とたんに尻餅 ついたんだ
遠い思い出 あの時の
父のぶかぶか 黒い靴
初めて会社に 出たときに
自分の甘さ 知らされた
挨拶の仕方 言葉ずかい
社会の常識 非常識
親父は家では 何一つ
会社のことなど 話さずに
ごろごろしてる 人だった
俺は馬鹿にし しかとして
会話もそこそこ 避けていた
言いたいことや 教えたい
父の気持を 分かってる
父のぶかぶか 黒い靴 |
親父が死んだ その後は
ピカピカ磨いて いるけれど
靴箱のなかで ひっそりと
履く人もなく 眠ってる
時々妻が 捨てようと
掃除の時に 言うけれど
思い出つまった 形見だと
親父の靴見て 言うんだよ
家族のために 黙々と
無口な父の 生き方を
近くで見てても 言わないね
父のぶかぶか 黒い靴
家族の為に もくもくと
働き続けた 父さんに
感謝してます 家族みな
ブカブカ靴が 見てるように
家族みんなも 知ってます |
作詩/野崎和俊(長崎県佐世保市) 作曲/能智星悟(愛媛県温泉郡)
世の中で家族の詩を読めば、圧倒的に母親に対する愛情の詩が多いように思います。しかし、父親が頑張って働き、家族を守らないと家族が大変な苦労をすることを案外大人になって感じる人が多いのではないでしょうか。
「父のぶかぶか黒い靴」は、そんな思いから、子どもの頃の父の靴の思い出や父子の関係等を、父への思いや感謝の気持ちを込めて書きました。

このページの先頭に戻る▲
福田智子「母への手紙 〜秋の夕暮れに」(作詞の部)
お母ちゃん 来たよ
元気な頃のあなたは
「よう来たなあ」とにっこり笑って
お父ちゃんとふたり 迎えてくれたね
今はそこに あなたはいない
仏壇にふたり並んで 少しだけ若い頃の
屈託のない 笑顔があるだけ
町育ちのあなたが 田舎に嫁いで
慣れない野良仕事をひとりでこなしてた
私が幼い頃 いつも畑にいて
牛や羊やにわとりを 一頭ずつ飼ってた
子牛は姉ちゃんの思わぬ病気で
売られていったっけ
なにもない 田舎の夜 娘たちを並べて
夜話を聞かせ毛糸を紡いだ
年の離れた姉ちゃんは 今も自慢げに言う
「お母ちゃんはなんでもできて 羊の毛を紡いで
編んで着せてくれたで」
なにもなかったけど その頃の私には
なにひとつ怖いものはなかった
お母ちゃんに守られていたんだと 今更に思う
もともと身体の強くなかった あなたのために
その後 お父ちゃんは田舎を捨て
みんなで町に住んだね
あなたは孫を育て 近所付き合いをして
家族を支え続けた
一番 輝いていた時代だったのかな
そんなあなたが 壊れていった
お父ちゃんが 大病と闘った短い夏の終わり
アルツハイマーと診断された
|
そわそわと落ち着かない日々
涙をこぼしたり 怒ったりもした
日暮れると 家を抜け出し
きつね川の土手を あてどなく歩いた
息を切らし 時に転びながら
町は秋なのに凍てついたように冷たくて
あなたは まるで見知らぬ外国の町で
迷子のように途方に暮れて 佇み私を見上げた
ひとは 徘徊というけれど
お母ちゃんのなかでは確かに
見えないなにかを もとめていたんだ
娘はただ隣にいて手をつなぐことしかできなかった
ああ なぜあの時 ぎゅっと抱きしめて
あげられなかったのか
私たちが あったかい胸に抱きしめて貰ったように
なぜ そうしてあげられなかったか
そうすれば お母ちゃんの胸のなかの
寂しさが溶けただろうか
今もわからないけど
ごめんねの言葉が いつも胸の奥にある
お母ちゃん この年になって
あの頃のあなたの いろんな喜びや哀しみや辛さが
よくわかるようになった
あなたがそうであったように
新しい家族の形に戸惑う日もある
でも あなたがそうして生きたように
生きてれば確かに
一瞬一瞬のしあわせが その中にあって
ああ 生きててよかったと 思える日々もあるんだ
あなたが逝った日が近くなった
居間にある数枚の写真
「いくのさん家(げ)」で撮ってもらったね
私の大好きなお餅つきの日の
まんまる笑顔にほっこりする
「よう来たなあ」とあなたが 言ってるようで |
作詩/福田智子(奈良市)
優しく強かった母が穏やかに自分をなくしていき10年闘いました。よく周囲のものの苦労が取り上げられ、家族とともに暮らすということができない病気だと言われます。確かに介護する者の犠牲がないと言えばうそになります。ただ、介護の中での喜びは忘れられません。人形のようになされるがままの寝た切りの姿には悲しくなりましたが、幸い姉二人との介護でしたので、終の棲家で最後まで暮らすことができました。
思い残すものは何もないと思っていましたが、7年経った今、いろんな思いがこみ上げてきます。

このページの先頭に戻る▲
新妻昭光・黒木祐里「ほおずき」(作詩・作曲の部)
母さん 私と植えたほおずき
庭にしっかりと芽が出ました
毎年夏になると きまって
幼い頃の思い出に ほおずきの話が出てきます
父と母を見送った日に
飾り付けたほおずきの話です
寂しさや悲しさを忘れるほど 真っ赤に色付き
風に揺れ 提灯のようだったと
今年のほおずきは いつもの夏よりきっと
赤くなりますよ 母さん
母さん 私が植えたほおずき
ぐんと大きくなってきました
夏の日差しが強くなっては
尖った先が薄赤く
そろそろほおずきが実ります
母がほおずきの種を取り
口に含んで鳴らした日のことが
昨日のように蘇ってきます
今年は母を迎えるための
お盆がやってきました
笑った写真には 綺麗な花輪のように
飾ってあげます 母さん |
|
作詩/新妻昭光(福島県いわき市) 作曲/黒木祐里(京都市)
独り暮らしだった義母(妻の母)を時々長期滞在させては、孫たちとの遊び相手になってもらっていました。人や自然を愛し、純真な子どもがそのまま大人になったような人でした。私といっしょに庭の花を手入れ、可憐さはないがどこか日本の野の花を思わせる「ほおずき」が好きでした。
94歳で亡くなりましたが、新盆には大好きだった「ほおずき」を飾ってあげました。
在りし日を思い起こし、母に語りかけるような「詩(歌)」になるよう心掛けました。

このページの先頭に戻る▲
湯浅広・吉岡重雄「春の日に・・・」(作詩・作曲の部)
春の陽気に誘われ
表に出たいと 言う母の
車椅子 押してゆく
風は仄かに 戯れ
土曜の午後を 軽やかに
女学生 駆けてゆく
充分長生きさせてもらって
幸せでしたとつぶやく母
ゆっくりとゆっくりと並木道
桜 花びら ふりかかる
|
子供みたいな 目をして
青空見上げる その母の
頬つたう 涙つぶ
風が冷たくなるから
そろそろ家に 帰りましょう
さみしそうに うなづいた
あなたの小さなそんな背中で
眠って育った 幼い頃
嘘のよな 夢のよな 歳月に
桜 花びら ふりかかる
あなたの望んだ そんな子供に
なれたでしょうかと車を押す
ささやかな したたかな人生に
桜 花びら ふりかかる
桜 花びら ふりかかる |
作詩/湯浅広(千葉県市川市)
年老いた母を車イスに乗せ、桜並木をいっしょに歩く幸せな日々はあっという間に過ぎ去り、人生の終わりに近づいてゆきます。それを見守る子、桜の花びらが降りかかり人生の来し方行く末を案じながらも深い絆で結ばれた二人を表現しました。
作曲/吉岡重雄(千葉県野田市)
友人の湯浅広氏が詩を書き、私が曲を付けました。残念ながら湯浅氏は亡くなってしまい、詳細はわかりませんが、私は彼の思いをくみ取り自分なりに意味を理解し、この詩にふさわしいメロディーを探し曲を付けたつもりです。桜並木の中、車イスを押す母と子のゆるぎない絆、そこに桜の花びらが降りかかる、そんな情景が浮かび上がれば幸いです。

このページの先頭に戻る▲
中尾壽満子「見つからない言葉」(作詩の部)
昭和22年1月14日 旧満州大連港出て4日目
玄界灘のうねりに酔い 船底に横たわっていた
人・人・人が 「日本が見えたぞ!」の声に
ふらつく足で 甲板へ駆け上がった
人の流れに従って 下船する一人ひとりに
散粉器で全身に ふりかけられるDDT
引揚援護局まで歩いた道程は
子供の足で 遠かった記憶しかない
支給された衣服に着替え
アルミ食器にたっぷり入った白米ご飯をかみしめ
かみしめた味は「覚えている」と弟妹4人
4人恒例旅行は 70年振りに佐世保
浦頭港からふるさとへ 帰ってきたコースを
十月に辿ってみよう となっていたのに
五月 悪性リンパ腫で 旅立った妹80歳
かける言葉も見つからないまま 新盆を迎える |
三枝ちゃんがほめてくれた詩 浄書します
風になびいて散っている
紅紫の萩の花に足が止まる
旧満州から引揚げ 落着いた母屋の庭に
咲き始めた萩の花を見て 母はつぶやいた
「ふるさとへ帰ったね」と
萩の枝をそっと手元に寄せ
「萩の花は蝶々の形だね」
紅紫の小さな花を 十二歳の私に見せた母
枝いっぱいに花をつける萩を
目を細めて見ていた母
風になびいて 庭に散る萩を
母はどんな想いで 掃き集めていたのだろう |
作詩/中尾壽満子(島根県出雲市)
旧満州大連から引き揚げ、2年後に母が36歳で亡くなりました。14歳の私が小さな母さん役。父は再婚もせず私たちを育ててくれました。背伸びしながら母さん役をする私を弟妹が手分けして家事、洗濯を手伝い、けんかをした記憶はありません。「よく育ったよね…」と、それぞれが自分の道を見つけ家族を築いていることを、父の三十三回忌を終え両親に感謝しています。
年一回は弟妹3人と私の4人で旅行する楽しみが、妹の突然の死で途切れました。淋しさと鎮魂の想いを込めて書きました。

このページの先頭に戻る▲